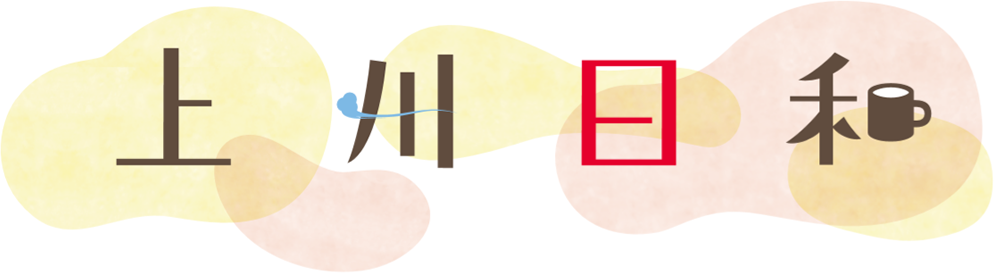
先週、東京上野の国立西洋美術館で20日まで開催中の「ルーベンス展」を観てきた。バロック美術を代表するルーベンスは、童話「フランダースの犬」の主人公ネロが憧れ、その前で息絶えた聖母大聖堂の祭壇画の作者だ。燃えるような色彩と官能的な人物表現、「絵筆の熱狂」と称された速い筆致で描かれた作品の前に立つと、そのパワーに圧倒された。
そんな大巨匠だが、イタリアで栄えた古代文化やルネサンス美術に憧れ多大な影響を受けた。本展では、彼が参考にした古代彫刻や絵画作品と、その表現を取り入れた作品を並べ、両者の関係性を浮き彫りにしている。現代の感覚では、芸術作品の模倣や表現の借用はタブー視されがちだが、彼の作品からは素直な敬意と探求心しか感じられない。
一方で彼は、肖像画や習作として家族や親しい人々を描いた。特に子どもの作品は、愛らしい表情や美しい肌、はちきれそうな肉体が今にも動き出しそうだ。こうした表現は、宗教画における天使などの描写に活かされ作品全体にリアリティーと魅力を与えている。
平成が終焉を迎え変動を余儀なくされる時代。自分自身、これからどう働き、どう生きるべきか頭を悩ませていたのだが、時を経てなお輝きを放つ彼の作品に一筋の光明を見た気がした。過去の偉業から素直に学び、かつ眼前にあるものと真摯に向き合い今に活かす。巨匠の姿勢は、変化に戸惑う現代の私にゆるぎない指針を示してくれた。
(野崎律子)